きのうもまた帽子を買ってしまった。3日前はハンチング、きのうはどうも名称が気になるが中折れ帽。
帽子に凝る気はないが、なんとなく気晴らしというか、散財したいというか。
どうせ買いたいだけですぐに飽きる、と言われることになるかもしれない。
日本のサラリーマンが帽子を被り、カバンを手にして通勤する姿は映画の中でしか見たことがないが、実際日本のサラリーマンはいつごろまで帽子を被っていたのだろうか。
一般的だったのは、主に大正時代から昭和30年代(1920〜1960年代)頃までです。特に昭和初期〜戦後しばらくは「ソフト帽+背広+カバン」が典型的な通勤スタイルでした、と言うのはコパイロット。
佐田啓二や高橋貞二の映画で見たような気がする。笠智衆もかぶっていた。
1960年代後半には、通勤に帽子を被る人はほとんどいなくなったらしい。
帽子を思い出す映画に「サブリナ」がある。日本公開のときは「麗しのサブリナ」という題名。
高校生のときに新宿のリバイバル専門の映画館で観たことがある。最近でもNHKBSなどで何回も放送されているが、制作されたのは1954年というから随分古い映画である。
オードリー・ヘプバーンが「ローマの休日」で一躍スターになってからの次作。「ローマの休日」ではハイネスだったが、この作品では大きなお屋敷のお抱え運転手の娘役。
「麗しのサブリナ」のラストシーンは、ひとり寂しくパリに行くことになったサブリナが船の甲板のデッキにいるとき、船のボーイが「あなた様に帽子を直してもらいたいというお客先から頼まれました」とサブリナに帽子を差し出す。
不審に思うがサブリナは、その帽子を直してボーイに返す。
ボーイはそれをもって船室に消えるが、その姿を追っても依頼人という人は見当たらない。
するとサブリナの後ろに、直した帽子を被ったライナスが歩いてくる。持っていた傘をすれ違った男性のコートの紐にひっかけて。
映画の中ほどにサブリナが、「パリでは帽子はこうしてここを折るの」「バリでは雨が降っても傘をさしてはダメ。パリは雨に濡れながら歩く町なの」とライナスに語るシーンがある。
実直なライナスは帽子を目深にかぶり、いかにも堅物であることを観る者に伝える。大会社の経営者だがしゃれっ気はない。
サブリナが憧れていたウィリアム・ホールデン扮する次男デイビットも帽子を被って出てくるシーンが多い。この時代アメリカでも帽子は一般的だった、と言うより日本人がアメリカの真似をしたということであろう。
デイビットはライナスと違ってハンサムでカッコいいプレイボーイ。帽子はいつもうしろかぶり。これが実に似合う。帽子は被り方で雰囲気が全然変わってしまう。
ボギーやホールデンに憧れて帽子を被ろうというのではない。
帽子が似合わないとよく言われてきた。人生終わりに近づいて、似合わないというものを身に着けるのも何かの刺激になるのではないか。
年取って女装趣味に目覚める人が多いという話を聞く。それも悪くないがとりあえず帽子を被ってみることにした。
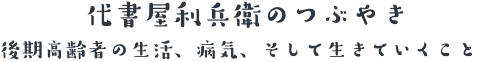



コメント