中学1年生の時バイオリンを手にした。貧しい母子家庭でバイオリンなど買えるはずもないが、母はお金を出してくれた。
楽器屋ではなく古道具屋で買ったのである。そのころ古道具屋があった。カメラから登山靴、布団、テーブルなど、ありとあらゆるものがごった返すように置かれていた。
バイオリンは店先からちょっと入ったところに、天井からぶら下げられていた。
学校からの帰り道、この店によって外からバイオリンを眺めていた。
いい色のバイオリンであった。値段はもちろん覚えていない。しかしその当時の母の財布からしては大きな出費であることは間違いない。
後で分かったことであるが、そのバイオリンは日本のメーカーの低価格品であった。状態はひどいものであったが、何も知識がないことが幸いして、そんなバイオリンでも真似事のように弾くことができた。
母は何故バイオリンを買ったくれたのか。ひとつの物語がある。
母は茨城県の霞ケ浦に近い農家の生まれである。名前は「よし」というがそれは10番目の子であったから、これでもうよし、という親の都合によるものだ。
誰よりも働き者だったと自分で言うが、10代の終わりごろ、東京のある実業家の家に行儀見習いということで女中奉公に出たことがある。
その家は今でもたいそうな屋敷が立ち並ぶ高級住宅街であり、その当主は後年大きな観光事業を創業する著名な人物であった。
その家にはまだ学生であった2人のお坊ちゃまと1人のお嬢様がいた。
長男様は慶応ボーイでハンサムで格好良かったという。
次男様は東大生で眼鏡をかけ、愛嬌のある人だったらしい。
門限の厳しい家であったらしく、帰宅時間が遅くなると表から、よし、よしと母の名を呼び、玄関を開けさせ、母に目配せをして家の中に入っていったという。
母はそのしぐさがとてもかわいい、と楽しそうに私たちに話をしたことがあった。(母は次男様のことを様づけの名前で呼んでいたが、これからも次男様と表記することにします)
次男様はバイオリンを弾く。母がときどきハイドンのセレナーデのメロディを口ずさむことがあった。どうして母がこんな曲を知っているのかと不思議に思ったことがあったが、どうやら次男様のバイオリンで覚えたらしい。
お嬢様はピアノを弾く。部屋から聞こえるデュエットに、母は田舎では経験することのないお金持ちの優雅な生活を感じたことだろう。
この次男様の名前と私の名前は実は同じなのである。母から、お前の名前は次男様の名前をつけたんだよ、と聞いたことがある。
だいぶ後になってから知ったことであるが読みは同じだが漢字の1文字が違う。名前は呼び慣れていても漢字はうろ覚えであったようだ。
母は次男様を好きになっていたのかな、と考えたことがあるが、多分そうではなく、奥様はいつもよそいきのような着物を着て、子供たちをお兄様、ちゅう兄様などと呼ぶような家庭というものに驚いたということだろうと思う。
あこがれもあったかもしれないが、お屋敷と田舎の生活は違いすぎる。あこがれるということにすら気がつかなかったかもしれない。
母にしてしてみれば大きなお屋敷、幸せそうな家庭と田舎にはいない大学生、バイオリン、眼鏡、母への愛嬌などは驚きであったのであろう。
1枚の古い写真が母の荷物にあった。お屋敷の門前でこの家族全員が写っている写真である。
私が31歳のとき、この次男様と偶然会うことになった。私の仕事の関係である会社を訪問した際、その会社の社長の名前が母から聞いていた名前と同じであったのである。
仕事の担当者に社長の経歴を訪ねると、あの観光会社の社長の息子さんである、という。次男様であったのである。
面会に応じてくれた。応接室に現れた次男様は長身で白髪で黒い縁の眼鏡をかけていた。今の私の年齢くらいだったのであろうか。
私は、「むかしお屋敷に女中奉公していたよしの息子です」、と自己紹介した。
次男様は、「よく覚えていますよ」とニコニコしながら答えてくれた。
「バイオリンは今でも弾かれますか」、と聞くと、「まあ、それは、もう」と笑っているだけだった。
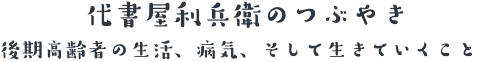



コメント