“お金持ち”が急増しているらしい。億万長者が165万世帯になったということなのだが、それだけでは分からない。億万長者と聞いて思い出すのは、「億万長者と結婚する法」というアメリカのテレビドラマである。
億万長者は2つのカテゴリーに分ける。純金融資産額1億円以上5億円未満を「富裕層」。5億円以上を「超富裕層」というらしい。
2年ごとに調査をするようだが、2021年の調査では、「富裕層」が139万5000世帯、資産額が259兆円。
「超富裕層」は9万世帯、資産額が105兆円。
それが2023年の調査では、「富裕層」が153万5000世帯、資産額が334兆円。
「超富裕層」は11万8000世帯、資産額が135兆円になったというのである。
「富裕層」「超富裕層」合わせて165万3000世帯。保有資産額は469兆円となる。全世帯数の3.0%で、金融資産全体額の26.1%を保有していることになる。
突然億万長者が増えたということではないはず。「富裕層」が「超富裕層」に、「準富裕層」と呼ばれる世帯が「富裕層」に昇格したということである。
世の中景気がいいはずはない。低所得者層が富裕層になるなどということは考えられない。富裕層はますます富裕に、低所得者層はますます貧困にという社会である。
富裕層が増えた要因は、アベノミクスによる大規模金融緩和であることは間違いない。金融緩和によるお金は、結局株式や為替、不動産というところに流れることになる。実体経済の牽引にはならなかった。
バブル崩壊で夜逃げをしたような人たちが生き返ったのは、大規模金融緩和政策のお陰である。そのことが顕著に表れているのが不動産業界。
超富裕層の中に、それこそ「町の不動産屋」と呼ばれている人たちが、かなりの数で入っているのではないだろうか。
リーマンショックの際、銀行の貸し剥がしがあったとはいえ、それも一時的なものであり、不動産業界は戸建てもマンションも、作れば売れるという時代が何十年も続いた。
バブル崩壊で破綻した不動産屋が低金利政策でよみがえり、破産して地元にいられなくなったような人が河岸を変えて成功している。特に有能な経営者ということではない。
失われた30年は、破産者を超富裕層にした時代でもあった。

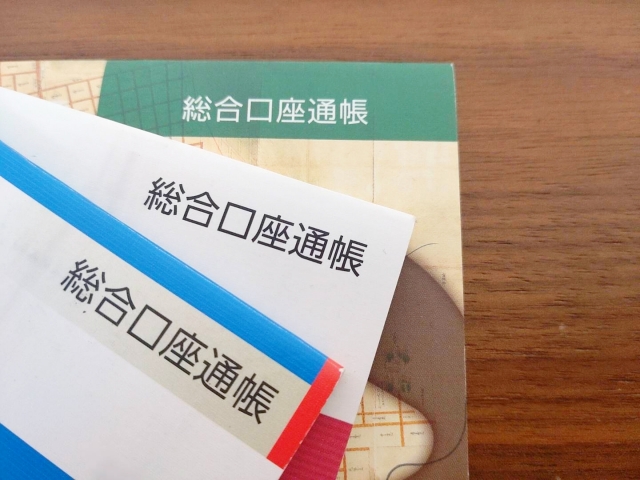


コメント