学生時代に学生オケに入っていた。今思うと、とんでもないことをやっていたのだと思う。
以下に書くことは私のことも含めてのことである。
皆とてつもなく下手なのである。下手というのは少しは弾けるということであるが、全く弾けていないのである。
ひどい者になる弓の上げ下げだけ合わせて音を出していない。
そんなことならオケにいる意味はないと思うが、舞台に立ちたいという思いは人一倍なのである。
管楽器は中学校や高校のブラスバンドで経験していればそれなりに吹けるが、弦楽器はどうしようもない。
楽器もとても楽器と呼べるようなものでない。少しでもまともな楽器を手に入れようという気もない。
音楽はスポーツのように根性でやるものではない。下手でもいいから弾くことが大事だ、などと言うことは音楽の世界ではあり得ない。
下手な者は弾いてはいけないのだ。今の学生オケにはこのようなことはないだろうが、このことが学生時代には分かっていなかった。
定年を迎えた人は、第2の人生でも、暇つぶしでも、何かのサークルに入ろうかなという気になる。
しかし音楽サークルのような、上手下手ということがある場合はサークルを吟味した方がいい。
上手下手があっても、例えば絵画サークルや写真サークルなどの場合は、他の参加者と関わりなく自分のやりたいことをやればいいが、音楽サークルは他人と関わることになる。
やはりサークルは上手な人のためのものになってしまうものである。
音楽に限らず力量というものはひと弾き、ひと筆で分かってしまう。
自分より下手だと分かれば人は横柄になるものである。音楽サークルとはそういうものである。
音楽をやる人にあまりいい人柄の人がいない、という感想を持つような経験を何度もしてきた。プロでもアマでもある。
日本を代表するオーケストラのコンマスの人が若い頃のコンクールにおいて、誰はばかることなくライバルの失敗を舞台袖で願っていたという。
その人のそばにいてその言葉を聞いた人からじかに聞いた話である。
誰もが1位になりたいであろうから分らぬ話ではないが、音楽の世界はそういうところである。
音楽をやる人にいい人柄の人が少ない。なぜか。音楽教育は人間教育ではないからである。
音楽には言葉がないから世界共通というが、言葉がないから人格が育たない。
イツァーク・パールマンは「感情をこめた演奏にすることは簡単である。私にはその技術がある」と言った。(了)

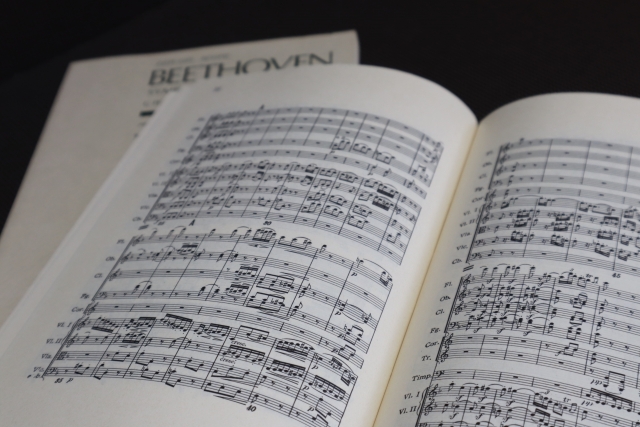


コメント