昔の漫才は、「青信号みんなで気をつけて渡ろう」、という常識的なものだった。
獅子てんや、瀬戸わんや。夢路いとし、喜味こいしなどの漫才は、当たり前の中にほのぼのとした面白みがあって、いわゆる悪い冗談というものはなかった。
「赤信号みんなで渡れば怖くない」、という漫才をしたのはツービートであった。言うまでもなくそのうちの一人はビートたけし。
悪い冗談というものはタブーである。たとえお笑いでも、悪い冗談というものは言うべきものではなかった。
しかしある時期から、ツービートの漫才あたりから、悪い冗談が闊歩するようになった。
もともと悪い冗談というものは意表を突いたものであるから、タブーをとりさってしまえば、「そう言われればそうだなあ」と人々は面白がるものである。
「赤信号みんなで渡れば怖くない」は、決して面白いフレーズではない。
しかしツービートの漫才は毒舌に満ちたものであった。毒舌は、身近な人が言う場合は聞き苦しいが、テレビから流れる分には面白いものとなる。
毒舌だから相方のビートきよしはビートたけしの毒舌に対応しようがない。結局彼らの漫才は、ビートたけし一人の毒舌漫談になるしかなかった。
ビートたけしはなぜこんなにも長期間テレビ界に君臨しているのであろうか。
彼は、若い愛人への取材に憤慨して、子分を10数人引き連れて、まさに「赤信号みんなで渡れば怖くない」と講談社を襲撃した人間である。
妻の妊娠中に不倫をしたとか、芸能事務所のしきたりを踏まずに芸能活動をしたとかで、それまで人気のあった俳優やタレントがずっと芸能活動から干されている。
ビートたけしは執行猶予付き懲役刑を受けている。どうしてそんな彼がいつまでもテレビに出ているのか。
滅多にテレビは見ないが、ちょこっと見ただけでもテレビの実情が分る。内容がないからである。
最近、新しい考え方なのか視点を変えただけなのか、という論調がある。
その例としては、すでに亡くなられた近藤誠医師のがんに対する考え方。そして最近では和田秀樹医師の認知症に対する考え方である。そしてさらに、ひろゆき、という2ちゃんねるの創業者の考え方である。
「患者よ、がんと闘うな」「好きな事だけやればいい」「食べたいものを食べる 」「血圧・血糖値は下げなくていい」 「がんは切らない」「肉を食べるなら朝から」「努力は1パーセント」「人とは関わらない方がいい」等々。
このような主張を新しい考え方とみるべきなのだろうか。どうもそうは思えないのである。
一言で言えば無責任な発言はないか。私はこれらの主張をしている著作を読んだわけではない。本の帯に書いてあることを拾っただけである。
それぞれの本を読んでみれば、それなりの主張の根拠は書いてあると思う。読めば納得するものであるかもしれないが、しかしそうだとしても多分無責任な内容にならざるを得ないのではないだろうか。
このすべての主張に共通していることは「人によっては」という言葉が省略されていることである。結局ビートたけしと同じで、視点を変えただけとしか思えないのである。

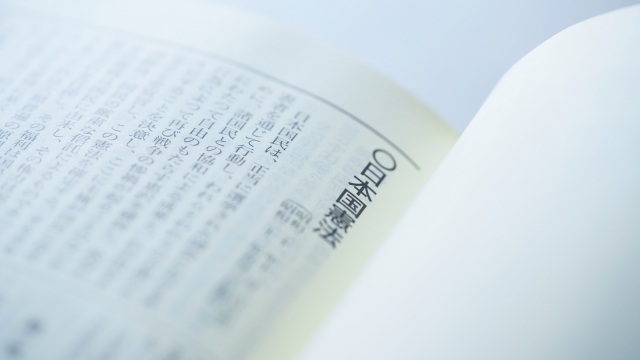


コメント