孤独死した従弟の遺産と言うべき書類を今日相続人に郵送した。
ご来訪いただいて説明しながら書類を渡した方が今後のためにも分かりやすいのでは、と案内状を送ったが、「行けない」という返事であった。
孤独死した従弟は義姉を頼らず、私の家内を緊急連絡先に指定していた。
親が再婚して、再婚相手の連れ子を養子にするケースは多くあるが、それによって養子と実子は兄弟姉妹になるといっても、互いにそれを知らない場合が多い。
ともかく昨年12月半ば、突如家内の身に降りかかった、相続人がいないはずの従弟の死に決着がついた。
92歳と66歳の相続人である母娘が、どこまで相続人としての義務を果たすことができるのか。気にならないということはないが、忘れることにする。
孤独死が多い社会である。ある知人は、家内と同じように突然警察から孤独死した遺体を引き取りに来るように、との連絡を受けたそうだが、それは年賀状からであったらしい。
警察は遺体の検案はするが、事件性がなければ遺族とか親族とかに関係なく、
関りのあった人に遺体引き取りを強制するようである。
孤独死ということに少し関係するかもしれないが、生活をしていく上で、法律の知識が必要なことを痛感する。
今でも日本の義務教育には、法律に関する科目はないのではないだろうか。
教育とは社会で生きていくための知識を身に着けることだと思うが、社会の決まり事というものを教える場でもある。
中学の教育科目に法律などを組み入れるべきではないだろうか。子供には法律は分からないということはない。民法や刑法の基礎を教えることは大事なことではないか。
日本の教育においては、実務教育は学問ではない、という考えがある。教育は学問、学問は教養であり、実務教育はハウツーものであるという認識がある。
ハウツーものはビジネススクールに任せておけばいいという考えがある。
大学の英文科では今でもシェークスピアを教えているらしい。確かに教養にはなるのだろうが、社会においてシェークスピアは役に立つのだろうか。
仕事をしていた頃、市役所の法律相談の相談者を何度かしたことがあるが、そのような場に来られる人たちの法律知識というものがあまりに低いことに驚いく。こう言っては失礼だが、「こんなことも知らないのか」というレベルである。わずかなことを知らないために、大きな損をしている人が多い。
小学校や中学校の社会科では、国会の仕組みとか国際社会における日本の役割をなどということを教えるようであるが、親子、兄弟、結婚、相続といった日常的なものが、法律の世界ではどう決められているのか、それを教えることは大事なことではないだろうか。
大学の法学部に入らなければ法律のことが分からない、というのはおかしなことである。
生活に関係することが、六法全書を見なければ分からない。六法全書を見てもどこに載っているか分からない。読んでも技術的用語ばかりで生活語になっていない、ということがそもそもおかしい。

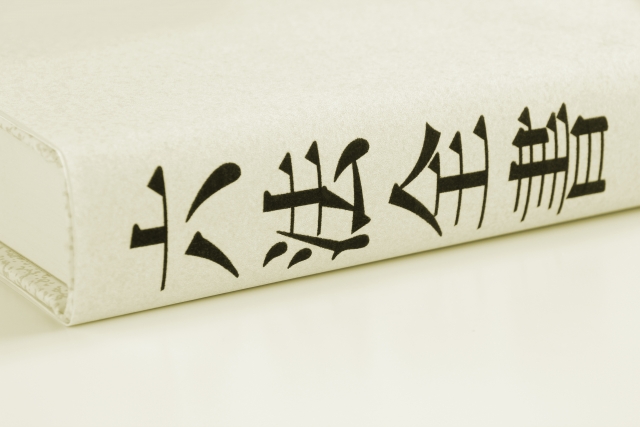


コメント