尾上菊五郎が体調により、3月の歌舞伎座公演を休演するという記事があった。
歌舞伎に興味はないし、一度も見た事もない私がこの記事に目がとまったのは2つの理由がある。
一つは菊五郎さんが私と同病の脊柱管狭窄症になったということ。
もう一つは60年近くも前の、NHK大河ドラマ源義経に菊五郎さんが出演していたからである。その当時は菊之助であった。
歌舞伎界からテレビドラマに抜擢されたということなのか、懇願されて出演したということなのか良く分からないが、とにかく歌舞伎界の御曹司がテレビに出ることは異例のことだったらしい。
原作者の村上元三は、彼以外に義経役は考えられない、とまで言ったそうだ。
うろ覚えであるが、確かテレビ画面に初めて映ったシーンは、義経に扮した菊之助が振り向いたときのアップされた姿だった。
当時23歳だったというが、何とも品のいい面長な顔立ちで実に美しい。
私は19歳であったが、男の立ち姿の美しさというのを感じたのはこの人が初めてではないかと思う。
このドラマを見るきっかけは菊五郎さんにあった訳ではない。このドラマの音楽を担当したのは武満徹さんだったのである。
当時私は武満さんに心酔、とまでは言わないが強い関心を持っていた。義経の音楽担当が武満さんと知ったとき、本当にわくわくしたものだった。
第1回目の放送が始まる時間帯にテレビの前に座り、N響と和楽器が織りなす武満の音楽に聞き入った。
いつも冷めた音楽を作る人に、このような高揚感のある音楽も作れるのかと、思い込みもあったかも知れないが感動した。
以来1年を通して、1回か2回くらいしか見逃したことはない。劇中に流れるメロディも義経の悲劇を表すような、今でも記憶に残る美しいメロディであった。
義経のドラマが終わった後もしばらく大河ドラマの音楽に関心を持った。
義経の2つ前の赤穂浪士は芥川也寸志さんが担当したが、あのテーマ音楽は大河ドラマ中最も人気のあるものではないだろうか。
間宮芳生、林光、一柳慧さんも担当したことがあるようだ。
最近の大河ドラマのことは全く分からない。1年にもわたり、人のつくった話の筋に一喜一憂するなど、我慢できない年になってしまった。
「歴史が学問によって語り継がれたことはない」という言葉は、ある大衆小説作家の言葉とされているが、その指摘を待つまでもなく、誰でもそう思っていることではないかと思う。
私が知っている義経も、秀吉も、赤穂浪士も、徳川家康もすべて映画や小説の世界のことである。
歴史の勉強というのは、中学や高校の時の歴史の時間に学ぶが、何を学んだのかといっても年表を思い出すくらいで、それも平安時代の前は何時代であったのか、鎌倉時代と足利時代はどっちが先だったか、ということすらはっきりしない有様である。
しかし「弁慶、死んでもなお我を守るか」と義経に言わしめるほど、弁慶の死は壮絶なものであったらしいし、秀吉は女性を相手にしたときの腰の使い方がうまかったらしい。
赤垣源蔵は兄の羽織を相手に今生の別れを告げたというし、家康は、秀頼の秀吉とは違う大柄な体つきを見て大阪城攻略の決心をした、ということを私たちは小説によって知ることができる。
こういう話は学問としての歴史では知ることができない。
歴史を学ぶことは大切な事と考えられてきた。歴史に学んで現在の生き方の指針にする、ということなのだろうが、どうもそういうことにはなっていないような気がする。
歴史は繰り返すというが、繰り返されるものにあまりいいものはない。いいものが繰り返されたという話も聞かない。
最近では、歴史を学ぶということは、人は歴史から何も学んでいないことを学ぶことだ、というある新聞の記事を引用させてもらってこの稿を終わりたい。(了)

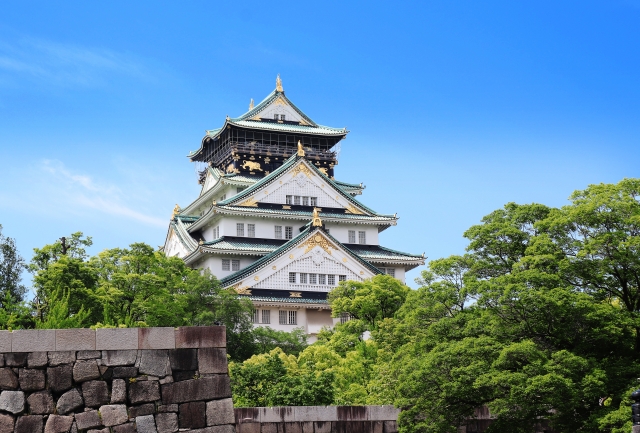


コメント