東京物語という映画は単調な、あまり物語性のない映画であるが、熱烈なファンが多い。小津安二郎監督作品として日本映画の中で特別な扱いをもって語られている。
最近では山田洋二監督が、リメイクと言っていいのか、同じようなストーリーの映画を作っているが、作らないほうがよかった。
何年か前には、外国の映画監督が選ぶ映画賞で第1位になったらしい。ともかく、この映画を知らなければ何も始まらない、というぐらいのことになっている。
尾道に住む年老いた夫婦が、東京に住む長男、長女に会いに行くが、子供たちはそれぞれ忙しく、久しぶりに会う親に特別やさしく接することもない。かえって迷惑だという感じさえある。
東京に来なければよかったということになるが、戦争で死んだ次男のお嫁さんはやさしく接してくれる。そして夫婦は尾道に帰る。
その後まもなく妻が亡くなり子供たちは葬儀に来るが、早く帰ることや形見分けのことしか関心がない。お嫁さんは一人残って義父との時間をすごす。
義父は、あなたはやさしい人だ、と言って妻の形見の時計を嫁に渡す。やがてお嫁さんも東京に帰り、一人尾道の海を見つめる父の姿で映画は終わる。
いつ頃作られたものだろうかと調べてみたら1953年。昭和28年である。敗戦からわずか8年である。新幹線もない時代に、老いた親が遠くに住む子供に会いに行くというのに、子供達は仕事が忙しいとはいえ薄情である。
あの焼け野原の時代から、こんな短期間でこんな家族の関係を描く映画が作られている。意外と言うか驚きと言うか。なにか信じられないものを感じる。
小津監督はこの映画で何を表現したかったのであろうか。お嫁さんとの関係は、あのやさしい笑顔がすべてである。この映画に長男、長女が笑顔を見せるシーンはない。原節子のあの微笑を撮りたくてこの映画を作ったのではないかとも思える。
小津監督は父親を演ずる笠智衆に、あまり表情を変えないように、と指示したという。つまり喜怒哀楽を表してはいけない、ということである。
ただ年寄りは我慢して、そして一人になり、孤独と寂しさの中に暮らすことになる。人生の絶望しかない。この映画は本当にいい映画なのだろうか。 (了)
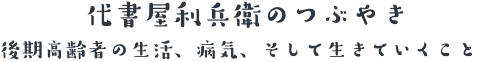



コメント