いつも歌謡曲が流れている街で育ったので、子供のころから歌謡曲は耳にしていた。
昭和20年代から30年代にかけて、東京下町の繁華街は、映画館街からもパチンコ屋からも商店街のスピーカーからも、歌謡曲は流れていた。
春日八郎が歌手デビューはしたがなかなか売れず、街をさまよい歩いているときに、パチンコ屋の店頭から流れてきた「赤いランプの終列車」に思わず涙した、という話はなかなかいい。
団塊の世代が物心ついたときに聞いていた歌手には、NHKの朝ドラの主人公である笠置シヅ子さんも淡谷のり子さんもいない。藤山一郎さんも記憶にない。知ったのは何年も後の懐メロ番組においてである。
美空ひばりさんの「東京キッド」も「リンゴ追分」も当時耳にした記憶がない。
女性歌手に記憶があるのは、島倉千代子さんの「からたち日記」から。
鮮明な記憶がある歌謡曲や歌手は、「哀愁列車」の三橋美智也。「別れの一本杉」の春日八郎あたりが始まりということになる。
戦後の苦しい時代を生き延びて、生きることの喜びを歌うのは、「リンゴの唄」や「東京ブギウギ」で終わったのかもしれない。
昭和20年代後半の歌にはつらく悲しい別れの歌が多い。
男から別れた歌がほとんどであるが、しかしいずれも別れの理由がはっきりしない。「惚れて、惚れて、惚れていながら行く俺に」というなら、別れなければいいと思うが、そうともいかなかったらしい。
詞というものは説明調であってはいけないというが、説明しようがないほど筋がない。とにかく別れなければ歌にならないというような歌詞である。
しかし男が別れる理由を明快に言えないにしても辛さはある。
「未練心につまずいて 落とす涙の哀愁列車」。「泣けた泣けた こらえきれずに泣けたっけ」。
女から別れて、女性歌手が歌うものといえば、時代がすこし後になるがちあきなおみの「喝采」くらいである。
歌手になるために「3年前 止めるあなた駅に残し 汽車に飛び乗った」ことになっている。
恋人を捨てたのに今日も恋の歌を歌って喝采を浴びている。でも本人はそれで満足しているという歌である。
女性が東京に行ってしまった歌もある。守屋浩が歌った「僕は泣いちっち」。「どうしてそんなに東京がいいんだろう」。この言葉は女性が言う言葉であった。
1959年、昭和34年の歌である。
「もはや戦後ではない」と経済白書にうたったのは1956年のことである。高度成長下、男が情けないものになっていくことを象徴するような歌である。
女に捨てられた男の話はどうでもいいとして、あの時代恋人と別れて東京に行った男たちは恋人のもとに戻ったのだろうか、あるいは恋人を迎えに行ったのであろうか。
「哀愁列車」や「別れの一本杉」から20年経って、太田裕美さんの歌う「木綿のハンカチ」がヒットした。
「毎日愉快に過ごす街角 僕は僕は帰れない」。都会の面白さに、恋人を忘れて故郷に帰らないという歌である。
作詞は松本隆氏である。昭和24年生まれ。まさに団塊の世代。26歳の時の作品ということになる。
団塊の世代として私と同じような疑問を持っていたのだろうか。
「木綿のハンカチ」では、男は遊びほうけてしまったから帰らない、という考えを松本市は示している。
男はみんなそうかもしれないと思うが、しかし女性の悲しみがハッキリと伝わってしまって余韻がない。歌はいろいろと思いめぐらすものがいい。
しかし残された女性が不幸になったとは限らない。遊びほうけるような男や、わけもなく自分勝手に別れるようなバカな男と別れた女性は、みんな幸せになっている。(了)
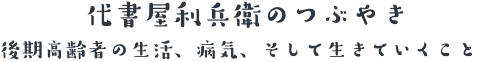



コメント