神奈川県藤沢市に住む和子さん(74歳)は、おととしの2022年6月、激しい痛みに襲われ、病院に救急搬送された。
乳がんが全身に転移し、医師が「延命治療を望みますか」と尋ねるほどの容体だった。積極的な治療はやめて自宅で療養生活に入った。
がんによる衰弱でベッドから動けない。午前9時過ぎと、午後5時過ぎの2回、30分以内の介護サービスを利用し、ヘルパーにおむつを替えてもらっている。
ヘルパーさんが自宅を訪れると和子さんは顔をほころばせた。
ヘルパーさんは和子さんのおむつをはずし体を拭く。皮膚の状態を見ながら乾燥防止のクリームを塗り、新しいおむつをつける。貯尿袋にたまった尿量、排便の量をチェックする。
「ヘルパーさんが朝おむつを変えに来てくれるとホッとする。天使が下りてきたような気がする」と和子さんは語る。
和子さんは要介護5である。訪問診療、入浴、リハビリなどのサービスを受けているが、中でも排泄の介助をしてくれる訪問介護を切実に必要としている。
朝のヘルパーが来る1時間前に食事を終え、排便のタイミングがおむつ替えに間に合うよう調整している。
うまくいかないこともある。昨年1月には真夜中におしっこがおむつ全体にあふれ、便も出た。寝ている夫を起こしたくないが、ぬれた体はどんどん冷えてくる。午前4時、我慢できずに泣き出してしまった。
和子さんの夫(76歳)は料理や掃除、洗濯、貯尿袋の取り換えはするが、おむつ替えまでは難しい。夫自身も前立腺がんの手術を2回受け、力を入れて動くと尿が漏れることがあるからだ。
「訪問介護のヘルパーさんに人間として一番大事なところをケアしてもらっている。生きる力をもらっている」。和子さんは涙をぬぐいながら訴えた。
「何かあってもヘルパーさんが助けてくれると思うから耐えられる。もし排泄介助がなくなったら、とてもやっていけない」と夫は言う。
以上は33日付毎日新聞夕刊に掲載された記事の要約である。記者は國枝すみれとある。
訪問介護の基本報酬引き下げが予定されていて、それによる零細訪問介護施設の運営危機が、和子さん夫婦のような状況にある人達に大きな影響を与えることになることを指摘したものである。和子さんは仮名となっている。
記者の文面にひかれてこの新聞を保管していた。
我々と同じ世代である。他人事ではない。明日の朝、和子さん夫婦と同じことになっているかもしれない。
病気になったら死ぬことが思い浮かぶが、治療できない、動けない、歩けない、トイレにも行けない、自分では何もできない、という事態があることをあまり想像しないものである。
夫婦の一方が倒れればその負担は計り知れない。夫婦二人倒れてしまえばどういうことになるのだろう。
排泄は汚いものであるが、和子さんが言うように、生きていることそのもののことである。
和子さんの世話するヘルパーさんはまだ若い人であった。和子さんを見守るその介護ぶりを正確に記者は書き伝えていた。努力に見合う報酬を制度は用意すべきである。
先の見えない状態の中で、和子さんの真夜中のおしっこの話は実に辛い話である。
生きるとはどういうことなのか。いつもここに戻ることになる。(了)
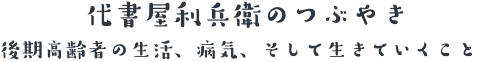



コメント