弦楽のためのレクイエムをはじめて聞いたのは中学生の頃だったと思う。
武満徹が自分と同じ結核を患う友人の死に際して作曲した、ということになっているが、武満さん自身がいろいろなことを言っているから本当のことは知りようもない。
静寂に包まれて始まり静寂で終わる。音楽を言葉にしても意味はないが、私はそんな印象を受けた。ところがこの曲を、沈黙から生まれて沈黙へと帰っていく、と表現している人がいた。
静寂でも沈黙でも、そうであれば音のある音楽そのものが存在しないのではないか、ということになるが、そう思わせる音楽なのである。作曲されたのは1957年、武満さんは27歳というから、ずいぶん若い頃から活躍を始めていたようだ。
レクイエムを悲しみの音楽と言うなら、この曲にはメディテーション(瞑想)と言った方が合っているような気がする。ストラビンスキーはこの曲について「こんなにきびしい音楽が、あんな、ひどく小柄な男から生まれるとは」とコメントしている。褒めたのかどうかは分からない。日本の評論家が、この曲には対位法がない、という指摘をしたこともあった。
ともかく少年の私には、この曲に何か深く感じるものがあった。普通なら感動と言っていいのだろうが、感動とは違う、感動しない感動と言っていいのか、うまい表現が見つからない。
武満さん自身は次のようなことを言っている。「はじめもおわりも定かでない、人間とこの世界とをつらぬいている音の河の流れの或る部分を、偶然にとり出したもの」
この言葉は何度も武満さんが口にしたことであり、彼の音楽を理解するうえで重要なものである。「偶然にとり出したもの」、まさかと思うが、しかしうまい表現である。詩のようである。
何も分かってもいないのに、ただ言葉の紡ぎに感動してしまう10代の少年には、別世界のような魅力的な言葉であった。
感動というものを考えてみる。武満徹は音楽から感動を無縁なものにしたかったような気がする。テクスチュアズ、ノヴェンバーステップスと、その後の作品を聞くと感動を避けているようである。音楽と音響はどこを境に異なるものになるのであろうか。
感動には嘘がある、とは武満さんは言っていないし、書籍の中でも書いていないが、音を自由にしたい、音を感動から解き放ちたい、というようなニュアンスのことは何度も著作の中で述べている。自分の仕事はまさにそのことに尽きる、というようなことを言っている。
音を自由にしたい、音を感動から解き放ちたい、などと考えて作曲をしたら、今までの音楽とは全く違うものになってしまうことは必定である。
高校3年の時に、第21回芸術祭参加という武満さんの作品集のレコードを当時6,000円も出して買ったが、そのタイトルは[WORKS OF TORU TAKEMITSU]であった。
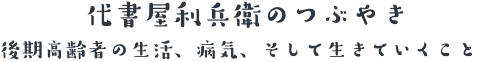



コメント