同性婚を考えると言っても、このところの地裁判決の検討とか、世界の趨勢とか、歴史的経緯とかを考えようというのではない。そんなことは新聞やウィキペディアを見れば十分に検証されている。
現代の社会に暮らす、一生活者としての知識で同性婚を考えてみたい。
私は同性愛者ではないから同性婚に興味も関心もないが、やはり同性の婚姻というのは異例のことである。人生滅多にこのような問題に遭遇することはない。年寄りの冷や水ということになるが、考えてみる面白さはある。
同性愛を法律的に認める必要があるか、という問題である。同性愛は人間の生活においてどのような位置づけになるのだろうか。
人は環境や周囲の状況によっては誰でも同性愛者になる可能性があるらしい。男性しかいない、女性しかいないという環境であれば、人は同性愛を求めることになる。
そういうことが頻繁に行われていたという事実は存在する。そういう環境や状況は日本の生活の中に昔から無数にあった。
同性愛を考える上で必要かどうか分からないが、昔から男性の女装趣味というものがあった。女性にも男装趣味があったのかもしれないが、男性よりは目立たなかった。
美しい男を見ると「男にしとくのがもったいない」とよく言ったものである。長谷川一夫の雪之丞変化はまさに女装趣味をメジャーなものにしたものである。いい男はいい女になる。人はそれを自然に受け入れる。女装趣味は同性愛につながるものかもしれない。
女装趣味というものは単なる嗜好ということなのかもしれないが、昨今、性というものが生物学的に解明されて、男であるが心は女である、ということがあり得ると認められるようになった。女装趣味というものも単なる嗜好ではなく、切実な心のうちの表現だったのかもしれない。
生物学的解明とは、胎児は常に女性として生まれ、胎内での成長過程において男性になるものは男性に変化していくが、男性になり切れなかった胎児というものも存在する、というものである。
姿は男だが心は女という人間がこの世に存在している、ということを認めることが同性愛理解の出発点となる。(姿は女だが心は男ということもあるが、ここでは男の立場から書く)
そんなことはあるはずはない、というのがそれまでの支配的な認識であった。政府関係者は「気持ち悪い」と言った。女装するのもオネエ言葉を使うのも、そういうことが好きなんだろう、という好奇の対象でしかなかった。
ひと頃シスターボーイという言葉があったが、もちろん軽蔑的な意味合いである。女っぽい男性をそう呼んだ。丸山明宏さんがそうであった。
シスターボーイを理解しうる社会的土壌はその当時全くなかった。しかし時代とともに個人の嗜好の問題ではなく医学的な問題になっている。社会が同性愛を考えなくてはならないことになったのはこの事によるものであろう。
同性愛を結婚という概念に取り込むことは明らかにおかしい。結婚は生殖を基本にしているものだからである。憲法には同性婚を否定する規定がないから、それを認めないのは憲法違反だという主張は成り立たない。
しかし同性者の共同生活という実体が存在しているのに、財産の継承や社会的手続きにおいて不便を強いられ、何らの救済方法もないという主張には同情するものがあり合理性もある。現行法制度の中で婚姻とは別に同性愛者のために法を定めればいい。そのような論調がこのところ目立っている。
しかし社会はあらぬ方向に向かっているようである。肝心な結婚制度なるものがおかしくなっている。結婚の減少。離婚の増加。結婚しても子供を産まない夫婦。結婚は生殖のための制度であるとするならその部分で婚姻制度は破綻していることになる。
現行民法に養子制度はもちろんあるが、同性愛者が養子をとって二人で育てたら、今の婚姻制度以上に婚姻制度になる。しかし考えてみると養子になる子供がいない。
同性愛という共同体の実体に対して、国がどう対応するかということである。
民法親族編は、実体が存在していてもその実体を登録しなければ法律効果が生じないことにしている。
実体そのものに法律効果を与えるような仕組みにしていない。婚姻届けを出していない夫婦は、夫婦関係があっても夫でも妻でもない。単に男と女である。
国民を管理統制するという意図があればこの仕組みが変更されることはないであろう。
国は同性婚を婚姻として認めるわけにはいかない。かつての家父長制度こそ最も日本にふさわしい家族制度だと信じている人たちが大きな力を持っているようだ。自民党政治は、このかつての考え方を否定する度胸はない。
同性婚は、日本人の消滅ということにつながるかもしれない。国を担う子供がいないのである。同性婚を祝福する気はなくはないが、同性婚の将来を考えると怖い話である。(了)
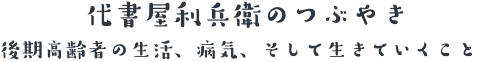



コメント