小学校の3年生の時、「冬の夜」という歌を習ったが、以来この歌が好きである。
明治45年の尋常小学唱歌に掲載された歌であるとされているが、作詞者、作曲者は不明となっている。文部省唱歌としてあえて作者不明としたのかもしれない。
「母は春の遊びの楽しさを語り、父は過ぎしいくさの手柄を語る」
戦後「いくさ」の歌詞は変えられたらしい。
ラジオもテレビもなかった時代。雪の降りしきる冬の夜の家族の団らんは囲炉裏端の語らいであったのであろう。
東京下町の母子家庭にはそのような団らんはなかったが、なんとなく思い描ける情景であった。
私が囲炉裏を経験したのは幼い頃、母の郷里でのことである。
居間に火がある場所がある。それだけで驚きであり、火が燃えることの楽しさを知った。
その家もその後建て替え、新しい家には囲炉裏は無くなっていた。
日本の家屋は暖房に対する配慮がないと言われている。思い出しても子供の頃の暖房は火鉢かこたつであった。家全体を暖めるという考えがない。
昔会津に旅行した時、お棺のような箱を見たことがある。冬、その箱に入って寝るのだという。厳しい冬の工夫なのであろうが、こんなことで寒さを防げるのかと思ったものである。
子供の頃、家にはもちろん囲炉裏はないが、家族の語らいということもあまりなかった。
母は子供たちと語り合うということより、どうして食べさせていこうか、ということで頭が一杯のようであった。
居候していた家の叔母は、ときどき私たちに火鉢を囲みながらいろいろ話を聞かせてくれたことがある。郷里の話が多かった。それも私たちに誇りを持たせるような話が多かった。
「高須崎波にゆらるる一つ松
さぞや山路の恋しかるらん」
この句は茨城県霞ケ浦の湖畔にあった大きな1本松を歌った句である。詠者は水戸の黄門様。
母や叔母にとっての母である祖母は大きな庄屋の娘であった。
祖母は馬の背に乗って、長い行列と共に輿入れしたという。その生家に昔、水戸の黄門様が立ち寄られ、休息されたことがあった。
この句はその時詠まれたものとされている。叔母はこの句をそらんじていた。
また先祖は武士であるという話もあった。郷里の馬頭観音は先祖が建てたものであるという。
いつの時代か知らないが、戦を逃れた武士が霞ケ浦に馬を乗り入れて逃れた。
馬は対岸にたどり着いた時息絶えた。それを憐れんで馬頭観音として祀った武士が先祖様だというのである。
叔母も子供の頃、囲炉裏端で親たちの話を聞いて育ったのであろう
大人の話が面白い時代があった。子供心にも楽しい話であった。
火を囲むということには人を結び付けるものがある。エアコンやクリーンヒーターでは人は寄り集まることがない。
子供を育てていた頃、せめて火鉢にでもしていれば、子供たちとよりよい関係を保てたのではなかったか。各室にエアコンをつけたら子供たちが集まるわけがない。
年老いて火を囲む。もちろん妻しかいない。囲む火は焼き肉用コンロである。
揺らめく薪の火を見たいがそうもいかない。
そういう火でもおにぎりを焼いていると心がほんわかとしてくる。
火を囲んで妻と語り合う話は他愛もないことであるが、そうであっても外に雪こそないが冬の夜である。(了)
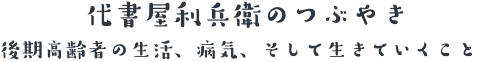



コメント