昨年亡くなられた池田大作氏は、「私が戦ったのは復讐のためだ」、という言葉を残しているらしい。
言葉の前後関係が判らないから何とも言えないが、池田氏と復讐とは意外と思うし、そうかもしれないとも思う。
人生には仕返しが必要だ、と以前ブログに書いたらあまり評判が良くない。
仕返しはしたところで結局虚しいものだということになっているが、しかしこれはしっかり仕返しをした人が、仕返しをした後に言う言葉である。やはり人生には仕返しをしなければ気が済まない、ということがあるのだ。
仕返しをしなければ気が済まないのは恨みがあるからだ、ということになるが、恨みにも命のことから心ない言葉までいろいろある。
恨みに対する仕返しには禁じられているものもある。近代国家においては仕返しは司法にまかせるしかないことになっている。
しかし、家族を殺した犯人は死刑判決を受けなければ遺族の恨みは晴れない。死刑を主張する遺族を非難し、殺人者を擁護するのは本末転倒である。
仕返しを学問の世界のことにしてしまっては、頭だけのことになってしまって、人の情というものに応えることができない。
仕返し、復讐となれば血なまぐさい話になってしまうが、日常の生活においては「言ってやった」というのも仕返しである。 この言葉で大体の仕返しはできるものであり、留飲なるものを下げることになる。
「言ってやりたい」人間が何人もいる。しかしなかなか「言ってやった」というチャンスがない。今度会ったら言ってやろうと思っているが、言わないうちに死んだり、所在不明になってしまう人間たちが増えてきた。
人間生きていくということは、どこかで人に恨まれ、人を恨むものであるということになっている。
そのためか恨みという言葉は多彩である。恨み骨髄、恨みを買う、恨みを晴らす。恨みを込める。恨みを飲むというのもある。まだまだある。如何に人生は恨みが多いかを示すものである。
恨みを買うとは難しい言葉であるが、人は恨みを買ってまで人を恨みたいものである、という理解も間違いにはならないのであろうか。
復讐といえばなんといっても「モンテクリスト伯」である。小学校6年生の時、巌窟王という題名で読んだことがある。
アレクサンドル・デュマという作者を知り、三銃士なども読んだが、こちらは冒険小説であっても時代背景などが面倒で、ダルタニャン、アトス、アラミスなどの登場人物の名前は覚えたが、筋はよく判らなかった。
それに比べモンテクリスト伯は、時代背景のいきさつがあっても、その復讐は単純明快で納得するものがあり、始めて我を忘れて一気に読んだ作品であった。
高校生の頃、原作全巻を読んでみたが、やはり痛快な復讐劇である。誰も殺していないのがいい。
この小説は、実際にあった事件をヒントにした新聞の連載小説であった。だからとても長い話になっている。読者が毎日の発行を心待ちにしたという。大変な人気があったというのもよく判る。
この小説で一番の気がかりはメルセデスのことである。
モンテクリスト伯がエドモン・ダンテスであることに気づいたのはメルセデスだけであった。
彼女はかつての恋人と夫の、二人の男性を失うことになってしまう。彼女にはなんの落ち度もない。どういうラストがよかったのであろうか。
メルセデスの悲しみから離れるが、「最大の復讐とは、その相手を完全に忘れてしまうことである」だそうである。
自分を捨てた男に対する女の復讐のことかも知れないが、女は天性として男を忘れることができるようだ。しかし男は忘れられたことに気がつかない。 (了)
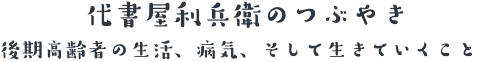



コメント