今朝の新聞に、事実婚と同性婚に関する記事が並んだ。
日本において結婚とは、役所に婚姻届けを提出することによって成立する。どんなに婚姻生活という実体があっても、婚姻届けを提出しなければ結婚ということにならず、事実婚と呼ばれることになる。
つまり婚姻とか親子関係というものは、国の制度に従うことによって認められるものとなる。
結婚に際し、夫婦は同じ姓になるように義務づけられている。夫の姓にしなければならないということではなく、夫または妻の姓ということになる。しかし9割以上女性が改姓しているらしい。この制度があるのは世界で日本だけであるという。
事実婚に関する記事では、新聞社が行ったアンケートの結果が掲載されている。国内主要企業約100社のうち少なくとも37社が、事実婚と法律婚を同等に扱うとする社内規定を設けているという。
結婚して女は家に入り夫の姓を名乗る。あたり前のことと思っていたが、世の中変わって来たらしい。
姓を変えたくないというニーズがあり、事実婚のままでは親子関係や相続関係において法律の定める利益を受けられないという不利益がある。
それだけでなく、夫が意識不明になって緊急手術が必要なのに、妻の承諾を認めないとする病院の取り扱いも常態化している。社会生活においても事実婚を認めないとする取り扱いになっている。
同性婚に関する記事とは、「同性婚を認めないのは違憲」とする名古屋高裁判決である。高裁による違憲判決は4軒連続で続いている。
本来保守と言われる裁判官が、時代のトレンドを身に感じているのかもしれない。しかし「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」という憲法の規定と、「同性婚を認めないのは違憲である」とする判決との整合性について、説明がなされたことがない。
夫婦別姓制度、同性婚の承認。個人のことであるが、国の在り方に関わることになるらしい。歴代の首相はこの問題について関心を示したが積極的に踏み込んだ人はいない。安倍さんあたりでは「とんでもないこと」であったようだ。
やおよろずの神の時代にまで遡るような問題でもあるらしい。
なにかそのあたりのことが、日本の政治にも文化にも人々の生活にも、靄のように視界をせばめているような気がする。
婚姻制度の変革が、日本の国としての在り方を根本から変えるものになるというならば、日本はたいした国ではない。
「国としての在り方」という言葉には、深い意味があるように聞こえるが、政治的意図に利用されているということもある。

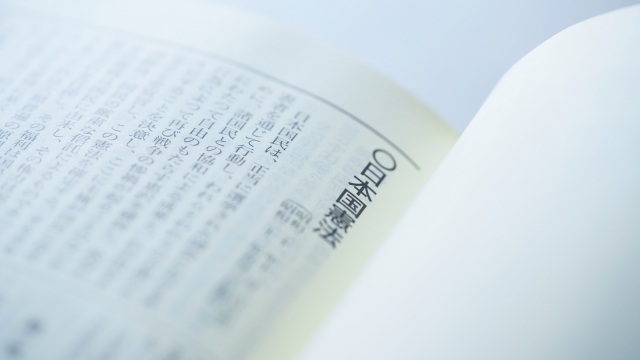


コメント