子供の頃犬を飼っていたことがある。
居候していた家の叔母が知人からもらい受けたものであるから、正確に言えば私が飼っていたわけではない。家に来たときは子犬であった。
そのころ家の中で犬を飼うという習慣はなかったから、幼犬のときは家の中の土間にミカン箱を置いて育て、成犬になってからは庭に犬小屋を作って飼っていた。
中型犬の雑種で茶色のふさふさした毛と黒い鼻をした雄犬であった。
多分私が一番喜んだのであろう。私はその時5歳くらいであった。土間に置いたミカン箱の中で一緒に寝た記憶がある。
名前はチルとなった。チルチルミチルからとった名前だと聞いている。
そのころチルチルミチルの話を叔母たちが知っていたようなのである。言うまでもなく童話「青い鳥」のチルチルとミチルの兄妹のことである。
世界名作童話など叔母たちが知っているはずはないのだが、幸せは身近なところにある、という青い鳥の話がその頃流行ったのかもしれない。
チルは成犬になって東京下町の原っぱを元気に走り回っていた。当時東京の下町には広い空き地が残っていた。そのころは放し飼いである。首輪に縄をつけるのは家に帰って犬小屋に入る時である。
私がハーモニカを吹くと気持ちよさそうにウォーン、ウォーンと歌った。
何度か見も知らないオッサンに怒鳴り込まれたことがある。チルに子供ができたらしいのだ。
叔母たちがどのように謝ったのか知らないが、今思えばチルは二枚目だったからモテたのであろう。
チルは4年程の間に3回犬殺しに捕まっている。犬殺しについて詳しいことは知りたくもないが、当時野犬狩りと称して保健所だったのか警察だったのか、野犬を捕獲する人たちがいた。
首輪をつけている飼い犬であろうが、つけていない犬であろうが、放し飼いになっている犬を捕獲した。
先を丸めた針金を投げ縄のようにして犬の首を狙うのである。
すばしこい犬をいとも簡単に捕まえる。子供心にも恐ろしい人たちであった。
犬殺しが来るとみんな大声で「犬殺しが来たぞ、犬殺しが来たぞ」と町中に声をかけた。
チルは私の目の前で捕まったことがある。最初に捕まった時である。
犬殺しは檻をトラックに積んで、犬たちが遊ぶ場所に乗りつけてくる。チルは犬殺しを見て激しく吠えたてた。すでに何匹もの犬が捕まっている。危険を察知していたのである。しかしチルの首は犬殺しの針金に捕らえられてしまった。
「チル逃げるんだ」。私は犬殺しの腕に噛みつこうと思ったのか、必死で犬殺しに向かって突進した。しかし幼い子供が大人の力に勝てるはずはなく、私は払いのけられて地面に転がってしまった。
チルは苦しそうにもがきながら、首にからんだ針金によってトラックの上まで釣り上げられた。チルの悲鳴を泣きながら聞いた。
あんな細い針金で犬を釣り上げるのである。「なんでこんなことをするんだ」と泣いて抗議する幼い言葉に、犬殺しはなにも答えようとはしなかった。
捕まった犬は千葉県の松戸の施設に収容されると聞いたことがある。飼い主がいる犬は飼主が引き取りに来てお金を払えば解放したらしい。引き取りに来なければ殺処分となる。
叔母はチルを引き取りに行ってくれた。犬を連れて電車には乗れないからタクシーということになる。犬を取り戻すのに多くのお金がかかったらしい。
2度目は私が学校に行っているときのことだった。学校から帰ると母が「チルが捕まってしまったよ」と言う。
母も居候の身、子供が可愛がっているからといって叔母に引き取りを頼むことはできなかったらしい。叔母も今度は助けに行こうとはしなかった。諦めなければならなかった。
ところがチルは脱走したのである。捕まってから何日も経ったある日、やせ細ったチルがよたよたと家の中に入ってきて立ち止まり、私たちの顔を嬉しそうに見上げたのである。
何日も何も食べる物もなく、遠い知らないところからこの家を目指して逃げてきた。幽霊になって帰ってきたのなら足がないはずである。母は思わず「チル、お前足があるのか」と叫んだ。
その晩私は、「もう家に入りなさい」という母の言葉をきかず、チルのそばから離れなかった。疲れ果てて眠り込んだチルの顔をいつまでも見ていた。
三度目は東京の下町から引っ越しをした高田馬場で捕まってしまった。高田馬場にはチルが遊べるよう原っぱはなかった。目の前は車が行き交う道路であった。
転校して間もないことであったから私が10歳くらいの時だったと思う。学校から帰るとチルの姿がない。母は、「さっきお宅の犬が捕まった」と近所の人が教えてくれたという。
チルとの永遠の別れになってしまった。チルはまだ5歳くらいであった。
高田馬場に越してからチルはクーンクーンとよく泣いた。私たちが住んでいるところとチルの犬小屋は少し離れていた。寂しかったのだと思う。
新しい町になじめなかったようである。チルの困ったような顔をよく思い出す。
犬を飼いたいという気持ちはいつもある。しかし犬との友情はチルだけにしなければという気持ちがある。
チルはいつも遠くを見ているような眼をしていた。自分の人生(犬生)を考えていたのではないだろうか。そんなチルを人間の都合で死なせてしまった。
私はチルと別れの言葉を交わしていない。忘れるわけにはいかないのである。(了)
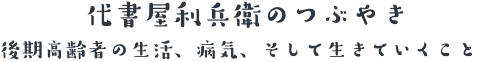



コメント