令和も5年目となった。コロナは令和1年の秋口から流行の懸念が指摘されていたが、3年経った今も収束の兆しは見えない。この3年、コロナのせいで家族そろっておせちを食べることができなかった。
何事にもあの頃が一番楽しかった、あの頃が華だったなあ、という時があるものである。
どこの家庭においても子供や孫が一堂に集まり、とりとめのない話をしながらでも、みんなで食事をし、顔を見合わせるということはやはりいいことなのであろう。
それこそが人生と思わなければならない。
私は今、その一番いい華の時にいるのかもしれないが、その大事な時をコロナに何年も邪魔されてしまったことになる。
今では考えられないことだが昔は来客が多かった。今以上に人同士の関係が密接であったのだろう。
とにかく正月と言えば、ひっきりなしに来る客のためにおせちをつぎ足し、お酒をお燗し、主婦は忙しい思いをしたものである。
妻の実家での義父のうれしそうな顔と、義母の忙しい中にも落ち着いた身の動きを思い出す。正月の賑わいというものがあった。
昨年亡くなった義兄夫婦も元気であった。あの家もあの頃が一番幸せな時だったと思う。
夫婦2人の祝いであるから何も特段な用意はしなくてもいい、と女房に伝えていたが、元旦の食卓はいつもの通りきれいに盛り付けられたおせち料理が並んでいた。いつ準備をしていたのであろうかと不思議に思うほどである
おせち料理は母から娘へ、娘から子へと、教え伝えられたものであろう。
妻の母は料理上手であったが、料理学校に通ったことがある女房の料理に感心したようなことが何度もあった。
勘に頼る料理から筋道を立てた料理になったのは江上トミさんの頃からだろうか。
私の母は田舎育ちで、おしんこと味噌汁というのが毎日の食事であったようだ。
料理を習うことなどできるはずもない。そんな母でもいろいろな料理を作ってくれた。しかし母の料理はなにより子供たちが腹いっぱいになることであるから、うまいとかまずいとかそんなレべではなかった。
ある時母はどこからかナポリタンを聴いてきて作ってくれたが、もやしが入っていた。焼きそばと同じようなものだと思ったらしい。
他の味を知らないから母の味をおいしいと食べていた。
結婚して、味噌汁は煮立てない、茗荷はさっと湯を通すだけ、ということを知った。どっちが正しいということではなく、確かにこの方がおいしいと思うようになった。
母はあの貧乏の中でもおせちは作った。
買い物に行っていつも立ち止まることがあったらしい。おせち料理に並べたい食材が買えないのである。
子供たちに食べさせたいが諦めて帰ることになる。母は並べることができなかった食材について、来年は食べようね、とよく言っていた。
そのうちの一つはカズノコのことであった。カズノコは私が生まれる前の時代にはそれこそ捨てるほどとれたらしい。北海道のニシン御殿である。
母はカズノコのおいしさを説明するとき、シャキシャキした歯触りのことを言っていた。
私たちが食べ盛りの頃カズノコは高嶺の花となっていた。今の時代で言えばカニのようなものであろうか。
母はハスや八つ頭などの煮物についてよくその縁起を口にした。多分自分の親から聞いたことなのであろう。
ともかく新しい年を迎えることができた。そして今年もまた妻の作るおせちをいただくことができた。
妻を亡くした人のことを想う。その寂しさの空白は孫のやさしさでも埋まることはないであろう。
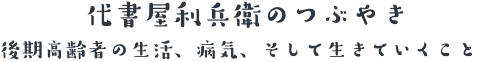



コメント